日本の音楽界最高峰の賞として知られる日本レコード大賞。
その長い歴史の中で、2年以上連続して大賞を受賞することは、アーティストにとって最も困難な快挙の一つとされています。
そんな栄誉ある連覇の記録は、いったい誰が、どのように達成してきたのでしょうか。
本記事では、日本レコード大賞の連覇記録を徹底調査してみました。
歴代の記録(何連覇が最高なのか)から最新の動向まで、詳しくご紹介していきます。
・日本レコード大賞の連覇記録について
(歴代の記録のまとめ・何連覇が最高なのか?)
日本レコード大賞の連覇記録について(何連覇が最高なの?)
では最初に日本レコード大賞の連覇記録について紹介していきます。
1959年に水原弘の「黒い花びら」が初代大賞を受賞して以来、日本レコード大賞は日本の音楽シーンを代表する賞として、多くのアーティストの目標となってきました。
毎年年末のTBS系列での授賞式は、その年の音楽シーンを総括する重要なイベントとして定着しています。
では日本レコード大賞の審査基準についてご紹介していきます。
日本レコード大賞の審査基準について
1959年の創設以来、日本レコード大賞は日本の音楽シーンの頂点を決める権威ある賞として、多くのアーティストの目標となってきました。
毎年年末に行われる授賞式は、その年の音楽シーンを総括する重要なイベントとして定着しています。
長年にわたり、審査では以下の要素が重要視されてきました。
・レコード売上実績
・音楽性・芸術性
・話題性・影響力
・パフォーマンス力
・メディアへの露出度
これらの基準は、時代とともに少しずつ変化を遂げながらも、音楽作品としての本質的な価値を見極める指標として機能し続けています。
特に近年は、ストリーミング配信の普及により、従来の売上基準に加えて、デジタルでの実績も重要な評価要素となっています。
ではこれらを踏まえた上で歴代の記録について紹介していきたいと思います。
日本レコード大賞の史上最高記録となる3連覇を達成したアーティスト
日本レコード史上最も多くの連覇は3連覇となっております。
この最高の栄誉となる3連覇という偉業を成し遂げたのは、EXILEと浜崎あゆみさんの2組のみです。
【EXILE】
「Ti Amo」(2008年)
「Someday」(2009年)
「I Wish For You」(2010年)
【浜崎あゆみ】
「Dearest」(2001年)
「Voyage」(2002年)
「No way to say」(2003年)
この両者の3連覇は、それぞれの時代を代表する音楽性と圧倒的な影響力によって達成された記録です。
EXILEはダンスミュージックの革新者として、浜崎あゆみさんはJ-POPの女王として、音楽シーンに大きな足跡を残しました。

どの曲もカラオケの定番曲ですよね!
日本レコード大賞で2連覇達成した歴代受賞アーティスト
2連覇の記録も、限られたアーティストのみが達成した栄誉ある記録です。
それぞれの連覇は、その時代のトレンドと音楽性を象徴する記録となっています。特に2010年代は、アイドルグループの躍進が目立ち、音楽シーンの変化を如実に反映しています。
【日本レコード大賞2連覇達成アーティスト一覧】
| アーティスト名 | 年 | 受賞曲 |
| 細川たかし | 1982 1983 | 「北酒場」 「矢切の渡し」 |
| 中森明菜 | 1985 1986 | 「ミ・アモーレ (Meu amor é…)」 「DESIRE」 |
| 安室奈美恵 | 1996 1997 | 「Don’t wanna cry」 「CAN YOU CELEBRATE?」 |
| AKB48 | 2011 2012 | 「フライングゲット」 「真夏のSounds good !」 |
| 三代目 J Soul Brothers | 2014 2015 | 「R.Y.U.S.E.I.」 「Unfair World」 |
| 乃木坂46 | 2017 2018 | 「インフルエンサー」 「シンクロニシティ」 |
それぞれの連覇は、その時代のトレンドと音楽性を象徴する記録となっています。
1980年代の演歌とアイドルの隆盛。
1990年~2000年代に燦然と輝く歌姫の時代。
2010年代は、アイドルグループの躍進が目立ち、音楽シーンの変化を如実に反映しています。
では次にこれら日本レコード大賞連覇曲が音楽シーンにどのような影響を与えたのか?
日本の音楽界の変遷を年代別たどりながら紹介していきたいと思います。
日本の音楽史と日本レコード大賞連覇曲が与えた影響について
ここまで日本レコード大賞で連覇を達成したアーティストとその楽曲について紹介してきました。
ここからは日本音楽史を振り返りながら日本レコード大賞で連覇を達成したアーティストがどのような影響を音楽シーンや社会に与えてきたのかを紹介したいと思います。
日本の音楽史と日本レコード大賞連覇曲が与えた影響 ①1959年〜70年代
この20年間は、連覇達成者が出ていない時期が続きました。
しかし、各年代を代表する名曲が次々と生まれ、日本の音楽シーンの基盤を形成していきました。
・歌謡曲全盛期
・美空ひばり、都はるみなど演歌の黄金期
・橋幸夫など若手スターの台頭
・ニューミュージック時代の到来
・フォークソング前世の時代
日本の音楽史と日本レコード大賞連覇曲が与えた影響 ②1980年代(演歌とアイドル)
1980年代には日本レコード大賞連覇をした方が二人おります。
【細川たかし】
1982-1983年
【中森明菜】
1985-1986年
それぞれが演歌歌手・アイドルとまるで対照的な二人。
まさにこの時代が演歌とアイドルの両方が前世であったことがわかると思います。
細川たかしによる演歌の連覇(1982-1983)
1982年と1983年で二年連続日本レコード大賞となった細川たかしさん。
受賞した曲とその特徴、そして社会的・音楽的に与えた影響についてまとめてみました。
【「北酒場」】(1982年)
演歌ブームの象徴的作品
全国のカラオケで大ヒット
年間売上100万枚突破
【矢切の渡し】(1983年)
・日本の風景を描いた名曲
・演歌の芸術性の評価向上
・幅広い年齢層からの支持
(社会的影響)
・男性演歌歌手の地位確立
・カラオケ文化との結びつき
・伝統音楽の現代的解釈
(音楽的影響)
・演歌の商業的価値の再確認
・世代を超えた支持の獲得
・日本の伝統音楽の継承
この細川たかしさんの連覇は、その後の中森明菜さん(1985-1986)の連覇へとつながる80年代の重要な記録となりました。
演歌とアイドルという異なるジャンルでの連覇達成は、日本の音楽の多様性を示す象徴的な出来事となっています。
では次に中森明菜さんについて紹介いたします。
中森明菜によるアイドルの連覇(1985-1986)
1985年と1986年で二年連続日本レコード大賞となった中森明菜さん。
受賞した曲とその特徴、そして社会的・音楽的に与えた影響についてまとめてみました。
【ミ・アモーレ(Meu amor é…)】(1985年)
・情熱的な歌唱力で話題に
・ラテン調の楽曲で新境地
・レコード大賞初の女性アイドル受賞
【DESIRE】(1986年)
・ロック調の楽曲で実力派としての評価確立
・作詞も手がけアーティスト性をアピール
・アイドル路線からの脱却を示す転換点
(社会的影響)
・歌唱力重視の評価基準確立
・アーティスト性との両立
・新しい女性像(アイドル像)の提示
(音楽的影響)
・アイドルの実力主義化
・楽曲の多様化
・女性アーティストの地位向上
これにより、80年代から90年代、2000年代へと続く女性アーティストの活躍の基礎が築かれました。
中森明菜の連覇は、後の安室奈美恵、浜崎あゆみへと続く女性アーティストの黄金期の先駆けとなった重要な記録と言えます。
日本の音楽史と日本レコード大賞連覇曲が与えた影響 ③1990年代
90年代は、日本の音楽産業が最も活況を呈した時期の一つであり、特に安室奈美恵さんの活躍は時代を象徴する現象となりました。
【音楽シーン】
「Don’t wanna cry」(1996年)
・R&B色の強い楽曲性
・ダンスミュージックの本格的な普及
・新世代の歌唱スタイルの確立
「CAN YOU CELEBRATE?」(1997年)
・日本のウェディングソングの定番化
・バラード曲における新しい表現方法
・年間売上200万枚を超える大ヒット
【社会的影響】
・「アムラー」現象
・ファッションリーダーとしての影響力
・若者の価値観やライフスタイルへの影響
・ストリートファッションの革新
・女性アーティストの地位の向上
・作詞・プロデュース面での関与
・パフォーマンスとルックスの両立
・海外進出の先駆け
90年代音楽シーンの特徴
では安室奈美恵さんが日本レコード大賞を連覇した1990年代の音楽シーンの特徴についてまとめてみました。
| 1990年代 | トレンド | 代表アーティスト |
| 前期 | バンドブーム | Mr.Children・GLAY |
| 中期 | ダンス系音楽 | 安室奈美恵・globe |
| 後期 | JPOP | 浜崎あゆみ・SPEED |
【1990年】
「恋唄綴り」堀内孝雄
「おどるポンポコリン」B.B.クィーンズ
【1991年】
「北の大地」北島三郎
「愛は勝つ」KAN
【1992年】
「白い海峡」大月みやこ
「君がいるだけで」米米CLUB
【1993年】
「無言坂」香西かおり
【1994年】
「innocent world」Mr.Children
【1995年】
「Overnight Sensation」trf
【1996-97】
安室奈美恵の連覇
【1998年】
「wanna Be A Dreammaker」globe
【1999年】
「Winter, again」GLAY
この時期は、CD売上の最盛期と重なり、音楽産業全体が活況を呈していました。
特に安室奈美恵の連覇は、単なる音楽賞の受賞以上の社会的影響力を持ち、後の浜崎あゆみや倖田來未といった歌姫世代の先駆けとなりました。
では次に2000年代以降についてご紹介していきます。
日本の音楽史と日本レコード大賞連覇曲が与えた影響 ③2000年代以降
2000年代に入ると、連覇記録が急増します。
音楽シーンの多様化とともに、強い個性を持つアーティストが次々と記録を打ち立てていったことは前述しましたが。
それらアーティとが与えた影響についてまとめてみました。
【浜崎あゆみ】2001-2003
・J-POP黄金期を象徴
・女性ソロアーティスト初の3連覇
・総売上1000万枚超えの実績
・女性ソロアーティストの地位向上
・ファッションアイコンとしての影響力
・作詞家としての評価確立
・アーティスト性と商業性の両立
・エモーショナルな歌詞
・強いメッセージ性
・女性の自己表現
【EXILE】(2008-2010)
・ダンスミュージックの革新
・パフォーマンス性の重視
・新たなエンタテインメントの形を確立
・EXILE TRIBEによる音楽事業の拡大・社会貢献活動との結びつき
【AKB48】(2011-2012)
・アイドルグループの新時代
・SNS時代のファン文化を確立
・選抜総選挙との連動
・ファン参加型
・メディアミックスアイドル文化の進化
【三代目 J Soul Brothers】(2014-2015)
・EXILEの DNA を継承
・新世代のダンスミュージック
【乃木坂46】(2017-2018)
・高い音楽性と表現力
・新しいアイドル像の確立
・新たなエンタテインメントの形を確立
・洗練された世界観
日本レコード大賞連覇という快挙は、単なる音楽賞の受賞以上の大きな影響力を持ちました。
各時代において、連覇を達成したアーティストは音楽シーンの革新者としての役割を果たしています。
日本の音楽史において、連覇達成曲は各時代のトレンドを確立すると同時に、次の時代への橋渡しの役割も果たしてきました。
では日本レコード大賞における最新動向と今後の展望について紹介していきます。
日本レコード大賞 最新動向と連覇の可能性
では、ここからは日本レコード大賞の近年の受賞傾向と変化について紹介した上で
2024年のレコード大賞がどうなるのかを紹介していこうと思います。
近年の受賞傾向と変化
2020年代に入り、日本レコード大賞は新たな時代を迎えているといえるでしょう。
デジタル化とグローバル化の進展により、評価基準も大きく変化を求められているのではないでしょうか。
・2020年:LiSA「炎」
・2021年:Da-iCE「CITRUS」
・2022年:SEKAI NO OWARI「Habit」
・2023年:Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
最新の音楽シーンにおける重要評価ポイントについてまとめてみました。
【配信実績重視】
・サブスクリプション再生回数
・音楽配信ダウンロード数
・SNSでの拡散力
【クロスメディア展開】
・アニメとのタイアップ
・動画コンテンツとの連携
・SNSでの話題性
【グローバル展開】
・海外での評価
・多言語展開
・インターナショナルな音楽性
このように時代に合わせて評価の基準明確にすることで視聴者にも納得のいく格式の高い賞レースを見せることができるのではないでしょうか。
では次に2024年の展望について紹介していきます。
日本レコード大賞2024年の展望
2024年の日本レコード大賞の展望ですが。
Mrs. GREEN APPLEの「ケセラセラ」が2023年の大賞を受賞し、2024年も優秀作品賞にノミネートされた「ライラック」で連覇を狙う展開となっています。
Mrs. GREEN APPLEがなぜここまで指示されるのかその理由についてまとめてみました。
・幅広い年齢層からの支持
・高いストリーミング実績
・楽曲の普遍的な魅力
このようにまさに今の時代にマッチしたアーティストであると言えるMrs. GREEN APPLE
果たして連覇となるのでしょうか?
他にも注目のアーティストについてまとめてみました。
【紅白初出場組の躍進】
・Creepy Nuts
・Da-iCE
・Omoinotake
【K-POP影響下の新世代】
・NewJeans
【デジタルネイティブ世代】
・BE:FIRST
果たしてどのアーティストが栄冠をつかむのか?
注目したいですね!
日本レコード大賞連覇の歴史と2024年展望について
ここまで日本レコード大賞の連覇の歴史と受賞アーティストや楽曲が与えてきた影響について紹介した上で2024年の注目ポイントについても説明してきました。
65年の歴史を持つ日本レコード大賞は、EXILEと浜崎あゆみによる3連覇を最高記録として、常に日本の音楽シーンの頂点を示してきました。
2024年、Mrs. GREEN APPLEが新たな連覇に挑戦する中、音楽界はさらなる変革期を迎えています。
デジタル化、グローバル化が進む現代において、レコード大賞の価値基準も進化を続けています。
近年は民意が反映されていない。
形骸化しているなどと批判されることもある日本レコード大賞。
今一度制度の見直しを図り、透明性のある審査基準の明確化によりこれらは改善できるのではないかと思っております。
今後も日本の音楽シーンの発展とともに、新たな記録が生まれることが期待されます。
ここまで読んでいただきましてありがとうございます。
【この記事を書いた人】

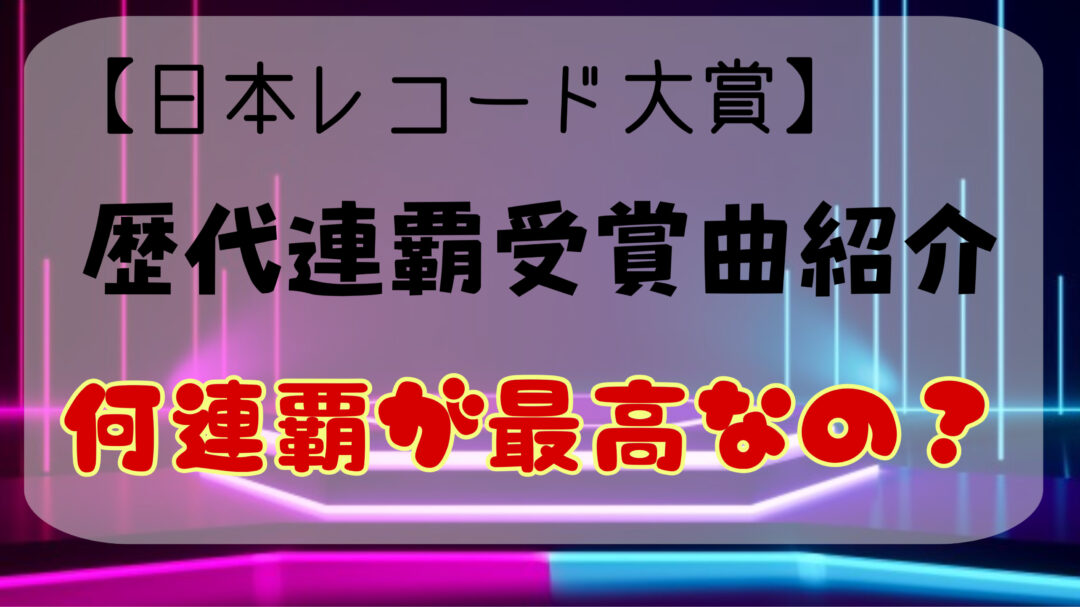

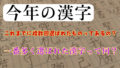
コメント